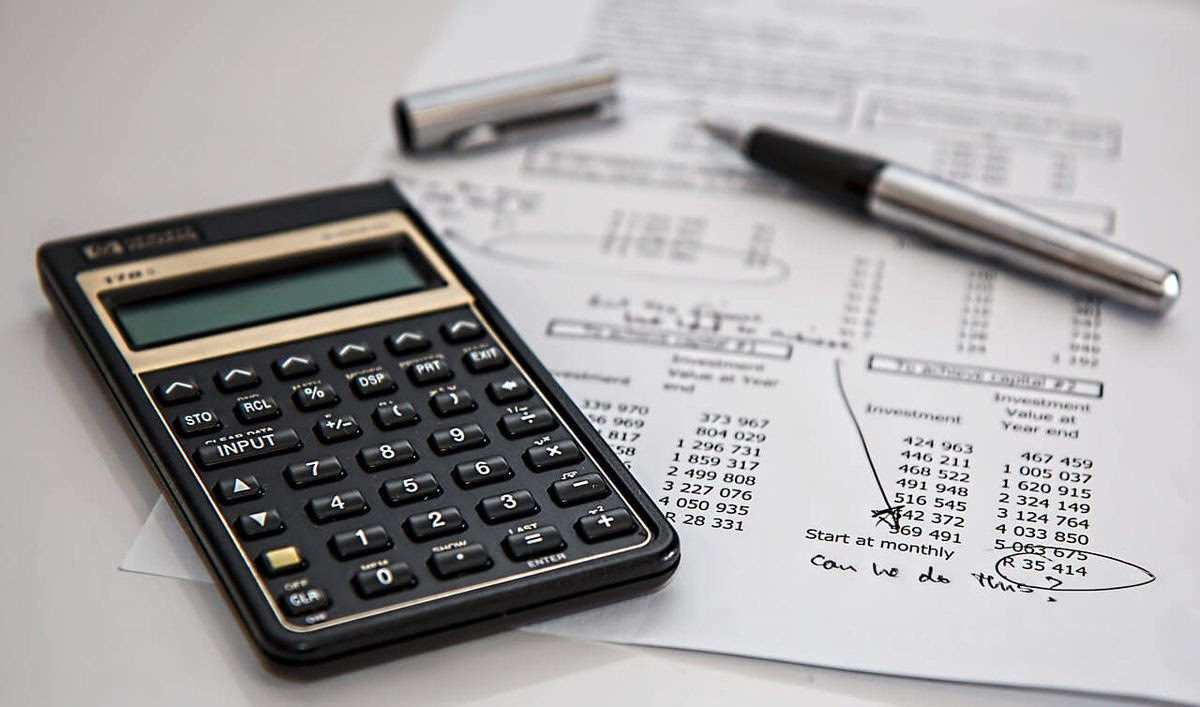この記事では、「産後うつ」「マタニティブルーズ」「産後クライシス」をママ、妻の視点からまとめました。
誰にでも起こりうるこれらを徹底解説!
ぜひご夫婦、ご家族で読んでいただき、情報と気持ちの共有に繋げてください。
産後うつってなに?【マタニティブルーズ】
私が長男を出産した直後に世界的パンデミックが直撃。
目に映るすべてがウイルスで、すべてが可愛いわが子に対する敵にまで見えていたし、テレビをつけると
類型罹患率や死亡率、ワクチンや新たな新型ウイルスまで、気分がドーンと落ち込む内容で溢れていました。
行政の産後サービスや一か月健診へ行くにも検温、マスク、消毒といった制限があり楽しい育児というよりは
未知なるウイルスからなんとしてでもわが子を守り切らなければ!と肩に力が入ったまま
はじめての育児がスタートしました。
今思い返すと、よぉあんな閉鎖的な環境で産後うつを発症せんと耐えたな~と。自分の知識と体験・経験から
頑張りすぎてるママパパに少しでも寄り添えたらと今回この記事をまとめました。
まず知っておこう、マタニティブルーズ
マタニティブルーズをご存じですか?
耳にしたことはあってもいまいちなんのこっちゃわからん!なんて方も多いかと思います。
最近では妊娠・育児雑誌、各SNSでも取り上げられていますが、まだまだ言葉だけが
独り歩きしているのも現状です。
マタニティブルーズとは、出産後2週間ほど続くブルーな気持ちで10人中8人ぐらいが経験します。
産後2週間程度で自然に軽減すると数々の書籍には書かれてありますが、産後1~2か月続きその後自然と
軽快しているママの方が多い印象を受けます。
一過性のホルモン変化と環境変化が原因とされ、時間の経過とともにホルモン状態が安定し、
赤ちゃんとの生活にも少しずつ慣れてくることで気持ちがほぐれていき、ママが笑顔を取り戻すという
プロセスですが、この生理的なブルーな時期にママにどれだけ温かく寄り添ってあげられるかが
重要になります。
この生理的なマタニティブルーズの時期に的確で、温かい支援が届かなけれなば、その後待っているのが
病的な産後うつというわけです。
第一子、第二子・三子...それぞれその時その時で状況も環境も変わります。
経産婦で経験しているからといって自分のホルモンをコントロールできるわけではありません。
妊娠前はポジティブな性格だった、専門知識がある、体育会系でメンタルには自信がある、など
こんな自分が?大丈夫やろ~と、まさか自分がと思っていても、
こればかりはホルモンが影響していることなので、誰にでも起こりうることだということを知ってほしいです。
 おかん
おかんホルモンに勝とうとせんでええで!
マタニティブルーズになって当たり前やで
多くのママが約一週間出産直後から入院し、その間に授乳や赤ちゃんのケアを一通り助産師や看護師から
教わりますが、まだ授乳が軌道に乗っていなかったり、家へ帰っても不安しかない状態で退院します。
産後は2週間健診または1か月健診があり、そのあとは自治体の助産師や保健師が産後3か月未満のどこかで
家庭訪問を1回ないし2回してくれます。
自治体によっては、産後うつが心配なママに対し専門的養育支援家庭訪問として4か月健診までの間
助産師が週に1回訪問するママサポート事業があったりします。
しかし妊娠前から良好な関係性があるわけでもない相手に、専門家だからといって
たった一回の訪問でどこまで自分の本音が話せるのでしょう。
健診の際に、育児支援のチェックリストを配布されママはチェックしますが、
本心でチェックできていますか?
自分の心のSOSに気づき、そのSOSを表に出すというのはそう簡単なものではないと思います。
妊娠が判明し約40週をかけて身体や心は妊娠ホルモンに適応しますが、産後は生まれた直後から
妊娠ホルモンから授乳ホルモンへドーンと切り替わるイメージです。
そりゃすぐに身体と心が適応できなくて、追いつかなくて当たり前なんです。
産後の健診が一通り終わっても産後状態はまだ続きます。これは産後うつの発症リスクが
依然高い状態であるということです。
ママ本人でさえも気づかないうちに無意識下で葛藤し、日々を漠然とした不安のなかで
過ごしていないか、迷路に迷い込んでいないか、鋭い観察力が周りには求められます。
産後うつってなに?【産後うつ】
産後うつとはどういった状態なのか
マタニティブルーズをきっかけにそこが軽快せず進んでしまった先にある産後うつ。
ママの心への重圧や心身のストレスをきっかけに、不眠、食欲不振、無気力、イライラ、
とにかく無条件にただ悲しい、強い罪悪感、愛着が持てないなどの症状が出てしまい、
赤ちゃんへの虐待やママの自殺を防ぐことが重要であり、専門家の支援や適切な治療が必要に
なるのが産後うつです。
誰しもがなりうるものではありますが、傾向として産後うつを発症しやすいリスク因子があります。
- 完璧主義者、生真面目。誰かに頼る、助けを求めることが苦手な性格
- 妊娠期や妊娠前にうつ病やパニック障害など既往歴がある
- 望まない妊娠により新たな環境になじめない
- ワンオペ育児、パパの育児参加が少ない環境
- 頼れない実家や人間関係、サポートを受けられる人が周りにいない
- 金銭面で育児に不安がある
- 仕事でキャリアを積んできた人
- 計画通りに進めたい、柔軟性がない人
- 育児の理想がある、理想が高い
まだまだリスク因子はありますが、細かく書き出せばきりがありません。
すべて当てはまらなくてもこの核家族が多い時代、一つくらい当てはまるママは少なくないと思います。
産後うつは、出産から1年以内に発症することが多い病気とされ、日本では約10%のママに
産後うつの症状が認められています。
産後1年以内の女性の死亡原因の1位がメンタルヘルス問題による自殺というデータもあります。
つまり産後うつは最悪の場合、ママと赤ちゃんの命を奪う恐ろしい病気であるということです。
それだけ産後のママの状態というのは不安定で支援が必要であると認識しなければならないのに、
学生時代に習うわけでもなく、妊婦健診で習うわけでも、母親父親教室で習うわけでもない。
産むまで、ママ自身がしんどくなるまで、産後のリアルな状況を知らない、学んでいないのだから、
そりゃ産後うつなるよ。そりゃパパ含め周りもサポート方法わからないよ。と思うわけです。
上記のマタニティブルーズでも述べましたが、退院後一通りの健診を終えてもまだなお
産後うつハイリスク状態であるということ、切れ目ないケアがママに必要だということを
社会全体で認識する必要が大いにあります。
赤ちゃんを産んだらすぐに待っているのが「母親である」という重圧、プレッシャー。
「子育て」という使命に燃え、どんどん自分を追い詰めていく姿が想像できます。
子どもの虐待が大きく世間で取り上げられているなか、ママに対し、産後うつに対し
フォーカスを当てた記事の数は少なく、あまり注目されていません。
だからこそ、不安を抱えるママ=要注意人物、なにかしでかす。のようなイメージが先行し、
自分が世間からダメなママだと判断されることを認めたくない気持ちや恐怖感から
世間の物差しでこうでなければとママがもっと頑張ってしまったり、SOSが出せなかったりして
負のループから抜け出せないように感じます。
「産後うつ チェックリスト」や「産後うつ イライラする しんどい」などネット検索すると
多くのチェックリストや記事がでてきます。
調べようとした時点でママ自身が自分に違和感を感じている、産後うつ予備軍になりうる状況であると
理解してほしいと思います。チェックリストの項目だけで判断せず、
チェックリストが一つも当てはまらないから産後うつとは無関係だと解釈しないでほしいです。
どこにそのきっかけが落ちているかわかりませんから。
出産のダメージから回復しきっていない身体にも関わらず、母乳を出そうと新たな段階に入るママの身体。
新しい生活や育児に不安いっぱい、悩み、戸惑い、気持ちよく眠れない、そんな怒涛の産後1年間。
ハイリスク状態であることを忘れず忙しいなかでも自分のSOSに気づき周りに頼れるママでいれたら、
ママ自身も赤ちゃんも守れるのかなと感じます。
マタニティブルーズと産後うつの違いは、生理的なのか病的なのかが大きく違うと理解してほしいです。
産後うつってなに?【産後クライシス】
マタニティブルーズ、産後うつとは似ているけど違うものに「産後クライシス」があります。
マタニティブルーズは妊娠・出産によるホルモンの影響で生理的に気分が不安定になること、
産後うつは妊娠・出産を経て、子育てへの不安や心身のストレスが原因で発症するうつ病という病気の
ことでしたが、産後クライシスは一体どういったものなのでしょう。
産後クライシス
そもそもクライシスとは危機という意味であり、産後クライシスは病名ではなく、
産後陥りやすい夫婦関係の危機を指す言葉です。
産後クライシスとは、妊娠前は良好な夫婦関係だったのに、出産後なぜかパパの行動の一つ一つが
鼻につき、イライラが止まらない。妊娠前のような夫婦関係、夫への態度や気持ちではなくなってしまう、
出産や育児を通して心身の変化や子育ての疲労で夫婦関係が悪化してしまう状況のことをいいます。
とくに妻から夫への愛情が変化し、冷めてしまうケースが多いようですが、夫婦互いに意見があり、
どちらが悪いとか、正しいという簡単な話ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っているということを
理解する必要があります。
妻は妊娠が判明してから少しずつ母へと変化していき、出産後はさらに母として本能的に小さなわが子を
命がけで守ろうとします。その結果、産後は夫にまで心を寄せたり、思いやることまで手が回らず、
夫への気持ちが減ってしまいます。
さらに母乳の分泌を促すホルモンには、プロラクチン、オキシトシンが含まれており、
このホルモンによってママは、まるでライオンの母のようにわが子に近づいた者すべてを排除しようと
攻撃的感情を抱いてしまいます。これが俗にいうガルガル期です。
産後の身体がまだ元に戻っていなくても、このホルモンによって自分の身体にムチを打ってでも
目の前の子ども(命)を守ろうとしてしまうのです。女性は母になると強くなるといいますが、
この二つのホルモンの作用で大胆不敵になるからですね。
(※ガルガル期とは医学的な言葉ではありません。子どもを守るために動物が周囲を威嚇することから由来する)
ですからたとえそれが赤ちゃんのパパであっても、大切なパートナーであっても、
ママと赤ちゃんの世界に入るわけにはいかないというわけです。
産後に妻が夫を遠ざけるのは、赤ちゃんを育てることを最優先にし、次の妊娠を避けるために動物的本能が
働いているからかもしれません。
産後の女性が性欲がなくなることが多い背景にはこのような遺伝子レベルの本能が要因の一つだそうです。
ここまで読み進めると、産後クライシスが悪いものに感じてしまいますが、心理学的には産後クライシスが
必ずしも夫婦関係が壊れかけていることを意味しません。
また研究結果として「夫婦間の親密な感情は、子どもが生まれてから2年の間は下がるが、3年を過ぎると下がった
レベルのまま安定し推移していく」と述べられており、産後2年間が夫婦関係を大きく変化させる
ターニングポイントといえます。
産後クライシスは一見「なんで私の気持ちがわからへんねん!」と妻から見た夫に対しての、
夫だけの問題に見えますが、
夫から見た妻に対しても「なんで俺のやる気を削ぐんや、こんなに協力しようとしているのに」と
妻の配慮ない一言に問題があるなど、夫婦ふたりの問題・課題であるということを認識していてほしいです。
産後クライシスに向き合わないでいると、産後うつにも繋がっていきます。
取り返しのつかないことになる前に、夫婦で向き合い危機に立ち向かって乗り越えてほしいと
強く願います。
夫婦で子育てをしている以上、クライシスは産後だけではありません。
入学をどこにしよう、反抗期がきた、思春期がきた、と子どもの成長に伴い夫婦で話し合い、一致団結して
危機的状況を打破する。きっとこれの繰り返しだと思います。
この団結を繰り返し繰り返し夫婦で経験することで、赤の他人から本当の夫婦となり、絆が絶対的なものに
育っていくのだと考えます。
先に待つ他のクライシスを夫婦で乗り越えるための練習、訓練だと思って、産後クライシスはしっかり
向き合ってみてください。毎日10分でもいいですから夫婦で話す時間がつくれると良いですね。
産後うつってなに?【ママに求められるスキル】
私は絵に描いたような、辞書で引いたら「おかん」と出てくるほどの大雑把でズボラな性格ですが、
ずっとずっと待ち望んでいた子宝に恵まれると、産後直後に新型ウイルスが大流行していたせいも相まって
いつまでガルガルしとんねん!と自分で自身をツッコむくらい、歯茎むき出しで威嚇しなが育児をしていました。
産院では、おむつの替え方、ミルクの作り方、お風呂の入れ方、市町村での育児セミナーでは離乳食の作り方など、
ネットや本になんぼでも書いてあり、少々言われたとおりにせんでも、要さえおさえていれば
自分流の育児方法で良いことばかり教えてもらっていました。ただあれだけズボラな私でさえも、ましてや
看護師、保健師である私でさえも、自分事となるとなかなか自分流の育児方法にシフトチェンジするのは難しく
こうでなければと知らず知らずに思い込んでいました。
私の方法と少しでも違った方法をする夫にイライラ。でも状況によっては、今は臨機応変に動かんかい!と
柔軟性を求めてまたイライラと、常に理不尽にイライラしていました。次第に「もうええ!私がやる!」と
意地を張り、しまいには気晴らしに一人時間を提案してくれた夫に対し「パパによぉこの子を預けへん」と
言うてしまう始末。
典型的なマタニティブルーズ、産後うつ予備軍、産後クライシスの三拍子そろった状態でした。
それでも最悪な結果に繋がらなかったのは、そっぽを向く私の顔を無理やりでも正面に向かせ向き合ってくれた
夫がいたからです。加えて第二子の妊娠が判明したことも大きかったです。
こうしよう、あぁしよう、次はこう!というスケジュールは見事に崩れる。それが育児なのですが、
まだ子どもが一人だとなんとか軌道修正できたんです。
でも妊婦で上の子を育児し、仕事もするとなると、ある日「あかん!もうええわ!むりむり!頑張りすぎやわ」と
自分の理想のスケジュールに子どもを合わせることが不自然であり、自分で自分を追いつめているだけと
ここでやっと気づけました。
育児の要はおさえつつ、手を抜くこと、頑張らんでええとこがわかるようになり、第二子が生まれ、
やっとこさ「頼る」ということができました。できたというよりは、頼らざるおえなかったのです。
周りを頼らないと、小さなわが子二人を自分一人で守れないと判断したのです。
頼ることの大切さを知り、頼れば周りの人が支えてくれる、人間ってあったかいなぁと感動しました。
母親に求められる育児スキルは、おむつが替えられるとか、離乳食が作れるとか、そんなことではなく
わが子のため、自分のためにSOSが的確に出せるか、頼れるかだと私は思います。



おむつや離乳食の前に、ここをまず最初に教えて欲しかったわぁ
これを読んでくださったママやパパは、わが子にどんな人になってほしいですか?
「なんでもひとりでやったんで~!自分が頑張ればなんとかなる」という人ですか?それとも
「ごめんやけど手貸して?」「大丈夫か?手貸すで!」と言える人ですか?
どちらも大切ですが、私は周りの人と手と手を取り合える人になってくれたらと願っているし、
そのためにはそうした母親の背中を子どもたちに見せようと意識しています。
赤ちゃんはママが思っている以上に強くたくましいです。もちろん未熟なので一人では
なにもできず、お世話が必要ですが育児書通り完璧かどうかは赤ちゃんにとっては重要ではないはずです。
頑張らんとこう!と力を抜いて育児をしてみても、産後うつは10人に1人が発症してしまう病気。
パートナーがいないなかでの出産・育児でも、実家や周りに頼れないママでも、どこかに
自分に合った頼れる場所があるはずです。
それが病院なのか、助産院なのか、行政なのか、SNS上なのかその人その人で違います。
産後うつになるのはだれの責任でもありません。
ママ自身が気づいていなければ、パパの出番です!ママを専門家のところへ
連れて行ってあげてください。ママに違和感を感じたまま放置するのはあまりにも無責任だと
思います。大きな失態をしないようにパパはママを見てあげてほしいです。
産後うつは正しく治療すれば治ります。精神科へ行くことは恥ずかしいことではありません。
歯が痛ければ歯医者へ行くのと同じです。心がしんどければ精神科へ行きましょう。
産後うつってなに?【まとめ】
産前産後はホルモンの影響により気分が不安定になります。とくに産後は夫婦で向き合うこと、周りに頼ることが
重要であり、これは産後うつを予防することにも繋がります。
産後クライシスはこれからさらに夫婦の絆を強めるための一つの試練であり、必ずしも悪いものではありません。
育児中、急に悲しくなったり、不安が襲ってきたり、私はダメなママだと思ったらまず子どもを客観的に
見てみてください。体重や身長は増え、日に日に逞しくなってきているのを感じませんか?
抱き上げたとき、重みを感じませんか?
ママが自分を責めていても、赤ちゃんはちゃんと育っています。わが子の成長発達がすべてを物語っています。
いつも子育てお疲れ様です。今日も赤ちゃんと生きてくれてありがとう。
私は本気ですべてのお母さんにこの気持ちでいっぱいです。